AIエージェント時代に必要なのは「実装しない勇気」
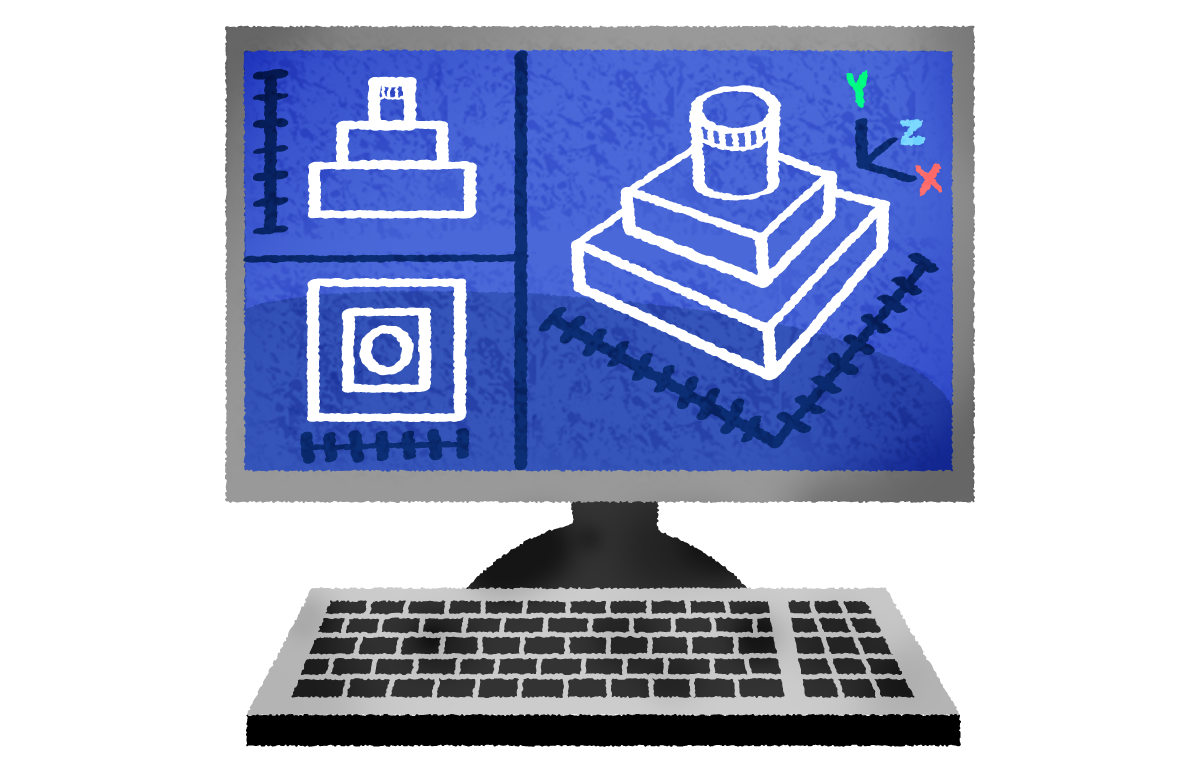
(執筆にChatGPTを使ってます)
はじめに
あなたがとあるWebサービスの開発チームを担当していると想像してみてください。
日々、顧客やユーザーから数多くの要望が届きます。
-
「この画面にフィルタ機能を追加してほしい」
-
「この通知はもっと細かく設定できるようにしてほしい」
-
「ダッシュボードに新しいグラフを入れてほしい」
どれももっともらしい要望で、実現できれば「便利になる」のは間違いありません。
しかし、すべてを実装していては開発リソースが持たない。
だからこそこれまでは「工数がかかる」「優先度が低い」といった理由で、多くの要望を見送り、取捨選択をしてきました。
ところが——AIエージェントが登場したことで、このバランスは大きく崩れつつあります。
実装コストが消えた時代
AIを開発に組み込むと、状況は一変します。
「この要望を実装してみて」と投げれば、数時間のうちに動くコードが出てくる。
テストやリファクタリングもAIが補助してくれるので、リリースまでの道のりも短い。
つまり、これまで開発チームを守ってきた「工数の壁」が消えつつあるのです。
その結果、チームにはこうした圧力が強まります。
-
「どうせAIで簡単にできるんだから、やればいいじゃないか」
-
「実装できるのに、なぜやらないの?」
AIは「できる」を常に突きつけてきます。
そして、人間は「できる」と言われると、心理的に「やらない」と言いにくくなるものです。
本当に大事なのは「できるか」ではない
しかし、サービス設計で本当に大事なのは「できるか」ではありません。
むしろ問うべきは「それを実装すべきか」です。
すべての要望を実装したサービスを想像してみてください。
-
画面はオプションで溢れかえり、どこで何を設定できるのか分からなくなる。
-
似たような機能が並存して、どちらを使うべきか迷う。
-
ユーザーが抱いていた「このサービスは○○ができる」というシンプルな理解が失われる。
つまり、ユーザーの頭の中のメンタルモデルが壊れてしまうのです。
サービスの価値は「できることの数」ではなく「分かりやすさ」や「一貫性」によって決まります。
実装コストが小さくなればなるほど、設計の重要性は増していくのです。
AI時代に求められる「実装しない勇気」
これまでは「工数がかかるから」「人手が足りないから」という理由で、要望を断ることができました。
しかしAIが実装コストを消してしまった今、同じ言い訳は通じません。
だからこそ設計者には、「なぜ実装しないのか」を語れる力が必要になります。
-
この要望を取り込むと、サービスのメンタルモデルが壊れる
-
類似機能との境界が曖昧になり、責務が混乱する
-
将来の拡張余地を狭めてしまう
そうした理由をきちんと説明し、顧客やチームを納得させることこそが、AI時代の設計者に求められる役割です。
実装する力よりも、**「実装しない勇気」**の方が価値を持つようになるのです。
守るべき設計原則
では、実装コストがゼロに近づいた時代に、設計者はどんな原則を持つべきでしょうか。
私自身は、次の5つが大切だと考えています。
-
メンタルモデルの一貫性を優先する
-
ユーザーが「このサービスはこういうものだ」と一言で言える状態を守る。
-
-
顧客の要望をそのまま積み上げない
-
機能ごとに実装するのではなく、抽象化や統合で応える。
-
-
インターフェースの責務を混ぜない
-
ひとつの画面やAPIが複数の目的を背負わないようにする。
-
-
拡張余地を狭めない
-
今は必要なくても、将来のニーズに応えられる柔軟性を残す。
-
-
「実装しない理由」を語れるようにする
-
「できるのに、なぜやらないのか」に対して、設計の哲学で答える。
-
これらはAIが代替できない、人間の判断にしか担えない部分です。
おわりに
AIによって実装コストが消えた時代において、設計者が直面する最大の課題は「何を実装するか」ではなく「何を実装しないか」です。
顧客の要望を無制限に取り込むことは、短期的には喜ばれるかもしれません。
しかし長期的にはサービスの一貫性を崩し、ユーザー体験を損ないます。
だからこそ今の時代に必要なのは、実装しない勇気です。
AIが「できる」を保証してくれる今だからこそ、人間は「やらない」と決断できるかどうかが試されているのです。