コード中心主義からコンセンサス中心主義へ(生成AIとの共創)
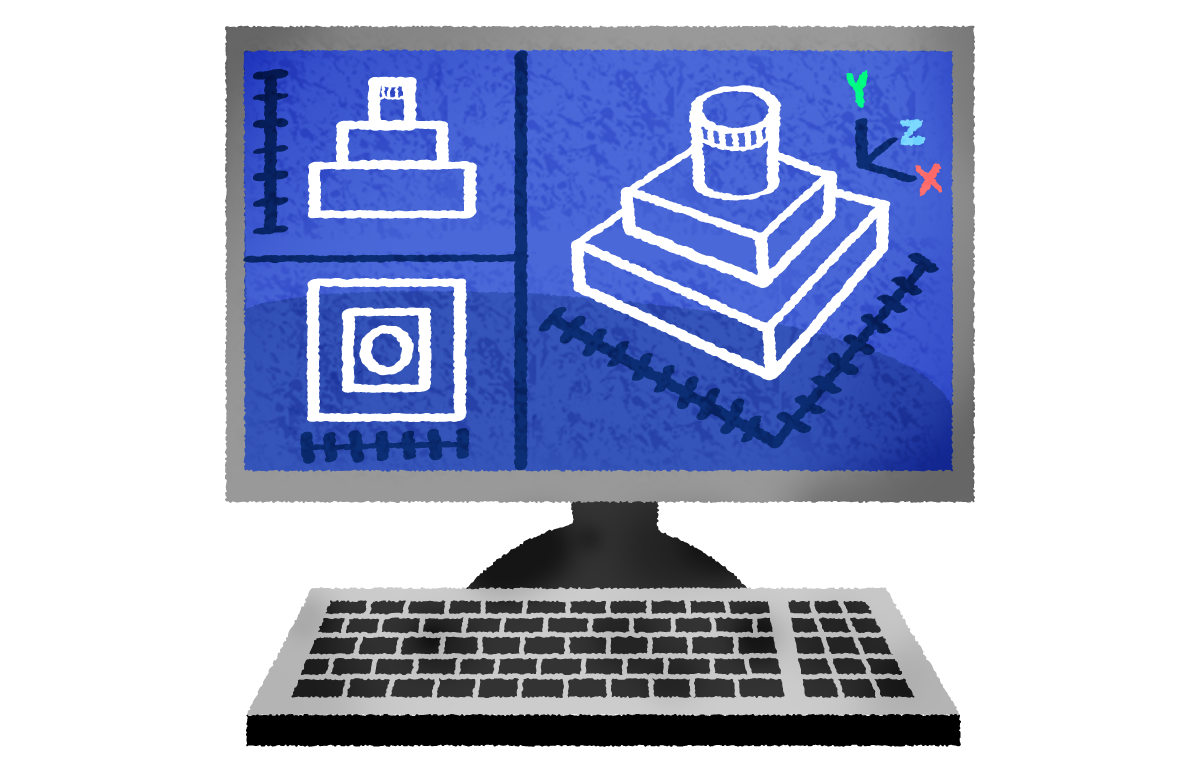
※自分の考えををChatGPTに掃き出してブログ記事にしてもらったものです。
コード中心主義からコンセンサス中心主義へ
かつて、ソフトウェア開発における本質はソースコードにあるとされていました。動作するコードこそが唯一の信頼に足る情報源であり、そこに書かれた記述がすべてを決定づける——それが「コード中心主義」の時代でした。
この価値観のもとでは、設計図やドキュメントはソースコードからの自動生成が理にかなっており、クラス図やAPI仕様の逆生成などが広く活用されていました。設計と実装の乖離を防ぐためにも、コードを起点とした一方向の情報流が当たり前だったのです。
ところが、生成AIの登場により、この前提が揺らぎ始めています。私自身の開発プロセスも大きく変わりました。
現在は、顧客の要望や業務背景を生成AIに共有し、課題をどのように解決するか、どういう方針で取り組むべきかを一緒に検討します。その対話の中で形成される「コンセンサス」こそが、開発の本質であると感じるようになりました。
このようなコンセンサスをベースに、生成AIに図やドキュメントを生成してもらいます。プログラムについても提案を受けますが、そのまま使えるケースは少なく、最終的には私が主導してテストや実装を行っています。
かつては「動くコード」がすべてだった価値体系が、「共有された意図や理解」へと重心を移している。この変化を私は「コンセンサス中心主義」と呼びたいと思います。
ただし、生成AIとの対話で得られたコンセンサスは、そのままでは保存や再利用が難しいという課題もあります。図やドキュメントは結果としての表現にはなりますが、背後にある文脈や意思決定の過程を十分に伝えるものではありません。
そこで私は、「コンセンサスのスナップショット」をどう記録するかが重要だと考えています。たとえば:
- 対話ログを要約し、キーワードや目的を付与する
- コンセンサスをMarkdown形式などで明文化する
- 生成された図やコードに注釈や背景をメタ情報として加える
こうした記録が、後の設計変更やメンバー間の共有において、大きな価値を持つはずです。
この「コンセンサスのスナップショット」という考え方は、ドメイン駆動設計(DDD)の「ドメインモデル」と深く関係しているのではないかと思います。
DDDでは、関係者の間で交わされた会話や理解を抽象化し、共有可能なモデルとして表現します。それは、設計と実装の橋渡しとなる存在です。
同様に、生成AIとの対話から得られたコンセンサスも、現代的なドメインモデルの一種と見なすことができるかもしれません。人間とAIが共に築いた理解を、図や文書、コードという形で定着させる——それこそが、今の時代のモデリングではないでしょうか。
生成AIの登場によって、開発における「本質」は大きく変わろうとしています。「なぜそうするのか」「何を共有しているのか」といったコンセンサスは、もともと開発において本質的に重要なものでした。生成AIの登場によって、それを明確にし、扱いやすくなったことで、より本質に集中できるようになったのです。
この変化に気づき、それを記録し活用する術を身につけることが、これからのソフトウェア開発において重要なスキルになっていくと感じています。
1件のピンバック
生成AIと共創するためのガソリン:コンセンサスの重要性 | 週記くらい